
|
■■ 北海道教職員組合【北教組】へようこそ
|
|||
 |
 |
 |
 |
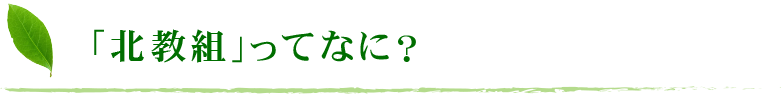
組合員は、小学校・中学校・高校・しょうがい児学校・幼稚園にいます。
道内における約1,700の学校には北教組の「分会」があり、179の市町村教育委員会ごとに「支会」「市支部」があります。


 |
|||||||||||
|
|||||||||||
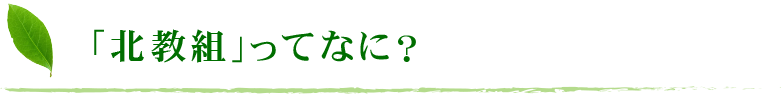 |
|||||||||||
| 「北教組」(ほっきょうそ)と略して呼ばれることが多いのですが、正式名称を「北海道教職員組合」といいます。北海道の公立学校職員などで組織している「労働組合」です。 組合員は、小学校・中学校・高校・しょうがい児学校・幼稚園にいます。 道内における約1,700の学校には北教組の「分会」があり、179の市町村教育委員会ごとに「支会」「市支部」があります。 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日精一杯頑張り、休憩時間も会議や仕事に追われ、家にまで仕事を持ち帰る。 「子どもたちのために頑張ろう。」という思いだけでは乗り切ることができないくらい、 今の学校現場にはたくさんの業務があります。 そんな忙しさの中、私たちは誰もが不安や悩みを抱えながらはたらいています。 人には言えず、一人きりで悩んでいる若手の皆さんも多いかもしれません。 そんな時、いったい誰に相談すればよいのでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
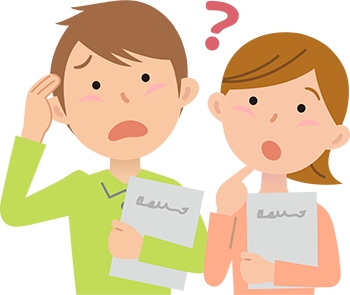 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道教職員組合(北教組)は、職場を大切にし、みんなで集まり、みんなで語り合い、みんなで学ぶ、そんな民主的な職場づくりをめざしています。 私たちは「ここに来れば仲間がいる」「ここに来れば安心する」「ここに来れば元気になる」そんなとりくみをすすめています。 興味のある方は、お近くの北教組組合員または北教組本部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
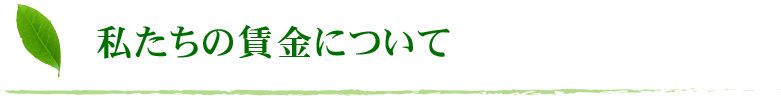 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちの賃金は交渉によって決定されます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たち公務員のストライキは、本来憲法28条によって保障されているにもかかわらず、公務員法(1948年国公法、 1952年地公法)によって一定の制限を受けており、人勧制度はその代償措置とされています。 しかし、代償措置とされる人勧制度はあっても、実際には長い間賃上げ勧告が行われても不実施や値切りがなされ、 完全実施がされない状況が続きました。 そのため、私たちは、図1に示すように要所において様々なたたかいを行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| まず2~4月に行われる春季生活闘争(春闘)によって、民間企業の賃金が決定します。次に、人事院が8月に、春闘によって決定された民間給与と国家公務員の現在の賃金を比較(これを「官民較差」といいます)し、国家公務員賃金の「勧告」(これを「人事院勧告」といいます)を行います。これを受け、9~10月に各都道府県や政令市等に設置されている人事委員会が、地方における公民較差を勘案し、地方公務員賃金の「勧告」を行います。なお、人事委員会の勧告については、表1の原則をもとに決定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちの賃金確定の流れ(図1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事委員会が「勧告」を行うために考慮される原則(表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| この「人事委員会勧告」を受け、私たち北教組は全道庁・自治労と組織する「地公三者共闘会議」において、道・道教委(札教組は、札幌市職連などと組織する「札幌市役所労働組合連合会」において、札幌市・市教委)と「年末賃金確定交渉」「年末賃金確定継続交渉」などの労使交渉を行い、具体的な方針を決定し、最終的には議会で条例を改定され、私たちの賃金が決まります。 私たちは11月からはじまる「年末賃金確定交渉」はもちろん、2月から始まる「春季生活闘争」「人事院勧告」など、節目においても他の労働者と連帯したとりくみを行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 教職員の休暇等の権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年次有給休暇(年休)
年20日間の年休があります。年休は「願い」ではなく「届け」ですから、年休処理簿に記入して提出することで行使できます。休む理由を記入する必要もありません。校長には「時季変更権」がありますが、年休をとること自体は変更できず、繁忙の度合いにより、別な日への変更を求める権限があるだけです。 7~9月の間で3日間、分割でとれます。これも理由は必要ありません。 ●パートナーが出産する場合 ●3歳に満たない子を養育する場合 ●子どもが病気になった場合 ●病気やけがをした場合 ●家族が、介護が必要な状況になった場合 ●身内に不幸があった場合 ●生理日に勤務することが著しく困難である場合 ●妊娠した時 つわり等で勤務することが困難な場合 ●出産時 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 教職員の労働時間
「北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」第3条により、「1週間の労働時間は38時間45分をこえてはならない」と定められています。そこで、1日当たりの勤務時間は7時間45分(=38時間45分÷5日)となるのです。 休憩時間は勤務時間に含まれません。勤務時間については、「北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第7条」により、「勤務途中、少なくとも45分の休憩を一斉に利用させなければならない」と定められています。ですから、出勤時刻から退勤時刻までは8時間30分となっているのです。 ただし、「休憩時間は、労働から完全に開放された自由な時間」とされていますから、休憩場所に拘束されることはありません。休憩時間は、労働基準法上、労働時間が1日に6時間を超える場合は必ず確保しなければならないとされています。 教職員は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(給特条例)第3条」によって、「時間外勤務手当・休日勤務手当は支給しない」「1か月の給料の4%に相当する額の教職調整額を支給する」とされています(労働基準法では、時間外勤務・休日勤務を命じる場合、25%上乗せした手当を支給することになっていますが、その適用を除外した規定です)。 そのため、「給特条例第7条」では、「原則として時間外勤務を命じない」と定めており、「時間外勤務を命ずる場合は、次の業務に従事する場合で臨時、または緊急にやむを得ない必要があるときに限る」とされています。次の業務とは、 1.生徒の実習に関する業務 2.学校行事に関する業務 3.職員会議に関する業務 4.非常災害に関する業務
|
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たち「青年委員会」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年7月から北教組内に設置されたいちばん新しい委員会です。 全道19支部の35歳以下の教職員19人で活動をしています。 主な活動内容は、全道合同教育研究会「青年のつどい」の企画・運営、各地での若者向けの交流会・学習会の企画・運営などを通し、若者の組織拡大をすすめています。 私たちの活動の様子は、「青年委員会だより」で全道に発信しています。 皆さんも一緒に活動してみませんか? |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||